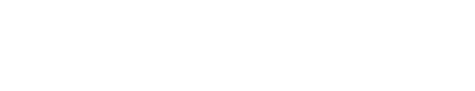「返還された敷金が低いのですが、どうしてですか?」 敷金の性格や、敷金によって担保される債権の範囲について
賃貸賃貸物件-
目次
敷金とは?
敷金は、賃貸借契約において、賃借人(入居者)が賃貸人(大家さん)に交付する金銭で、契約上賃借人の債務を担保する役割を果たすものです。
賃借関係が終了し、賃借人が退去する際に、賃借人に未払い賃料があったり、建物の原状回復のために費用が必要になった場合には、賃貸人は、敷金の中から、それらに相当する費用を差し引いて、残金のみを賃借人に返金すればよいということになります。
敷金は、賃貸人にとっては、重要な「安心・担保」の仕組みです。
-
敷金から控除できる範囲は?(敷金によって担保される債権の範囲)
敷金を入居者に返還する際にどこまで控除してよいのかは、賃貸人にとっても、賃借人にとっても重要な関心事です。
そこで、以下では、敷金によって担保される債権の範囲について、具体例を挙げて説明していきます。
-
未払い賃料
まずは、もっとも典型的なものとして、未払い賃料が挙げられます。賃借人は、入居期間中、契約で定められた賃料を、大家さんに対して支払う義務があります。
この支払いが滞り、賃貸借契約が終了して建物を明け渡すときに未払いが生じている場合には、賃貸人は敷金の中から未払い賃料相当額を領収した上で、残金を返還すればよいとされています。
賃料の支払いを滞納した場合には遅延損害金も発生しますが、この遅延損害金も、敷金で担保される範囲に含まれます。
-
明け渡しが遅れた場合の賃料相当額・損害金
契約終了後に賃借人が速やかに物件を明け渡さない場合、賃貸人は、新たな入居者を募集することができなかったり、新たな入居者に貸すために必要な清掃作業などが行えなかったりと、賃貸人にとって困った事態が生じます。
賃貸人は、本来であれば次の入居者から賃料を得ることができるのに、それができない期間が生じてしまうということです。
このような場合、賃貸人は、賃借人に対し、明け渡しまでの間の賃料相当額等を、損害金として賃借人に請求できる場合があります。
このような、明け渡し遅延による損害金も、敷金から控除される債権の範囲に含まれます。
そこで、契約終了日を過ぎても荷物を残していたり、鍵を返さなかったり、清掃や修繕作業の立ち合いを拒んだりした場合には、賃借人は、明け渡しを遅滞しているとして、その間の賃料相当額の支払いを求められ、それらが敷金から控除されてしまう可能性がありますので、注意してください。
-
原状回復費
賃借人が、故意または重過失により、壁・床・設備等を損傷させた場合や、契約で定められた使用方法を守らなかったために修復が必要になるようなときは、原状回復のために必要になった修繕・復旧費用を、敷金から控除される場合がります。
例えば、「ペット飼育は不可」という契約だったにもかかわらずペットを飼っていたため、壁や床に大きなひっかき傷ができてしまった、といった場合には、賃借人が壁の修理費用の負担を求められる可能性があります。
(もっとも、通常損耗や経年劣化による損傷は、原則として賃貸人側で修理費用を負担することになるので、その場合は敷金から費用を控除されることはありません。)
以上が敷金から控除される可能性のある費用のうち、代表的なものになります。
トラブルにならないようにするために、契約時に、使用方法の定めがあるかどうかや、敷金から控除される費用についての定めがあるかどうかについて(定めがなくても上記費用等は控除される可能性が高いですが、一歩進んで上記以外の費用についても控除の定めが記載されているケースもあります)、確認をしておくとよいでしょう。
また、退去時・明け渡し時には、賃借人・賃貸人双方で立ち合いのもと、室内の損傷・汚損の状況を確認し、必要に応じて写真や動画に残したり、チェックシート等を利用して記録しておくと安心でしょう。
-
賃借人のほうから「敷金を未払い賃料に充ててほしい」と請求することはできません
賃借人が賃料を用意できない月があったとして、賃借人側から「今月の家賃分を敷金から領収してほしい」と賃貸人に請求することはできません。
敷金は、明け渡しまでに生じる債権を担保するものですから、賃借人側に敷金返還請求権が発生するのは「賃貸借契約が終了し、明け渡しがなされた後」になります。そのため、賃貸借契約が続いているうちはもちろんのこと、賃貸借契約が終了して以降も、賃借人が明渡しを終えていない・鍵を返さない・現状回復の立会いを拒んでいるなどの状況があるうちは、賃借人は、敷金の返還を求めることはできません。
加えて、明け渡し後であっても、未払い賃料等を敷金から回収するかどうかは、賃貸人が決めることであり、賃借人から充当を請求することはできません。
-
賃借人の建物明け渡し義務は、賃貸人の敷金返還義務に対して、先に履行される必要があります
先ほど、敷金返還請求権が発生するのは、「賃貸借契約が終了し、明け渡しがなされた後」であると説明しました。改正後の民法第622条の2第1項では、「賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに、受領した敷金の額から賃借人の債務を控除した残額を返還しなければならない」と規定されています。
ここで重要なのは、「賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還(=明渡し)を受けたとき」が返還義務発生の前提となっていることです。つまり、賃借人が明け渡さない間は、大家さんが敷金を返す義務は生じないということです。
このため、実務的には「賃借人が部屋を明け渡すこと(建物・設備・鍵の引渡し含む)」が先に履行され、それが完了して初めて、敷金の清算(未払賃料・修繕費等の確認・控除)→返還、という流れになります。
最後に
以上が、敷金の性格、敷金から控除される債権の範囲になります。
敷金からの控除の範囲でもめないようにするためにも、賃貸借契約をするときは、契約事項をきちんと確認した上で、契約期間中は、賃料の支払いや物件の使用方法についての約束を守り、損耗等で気になる部分があるときには写真に収めるなどして記録をとっておくなどすると良いと思います。
監修:弁護士 前田ちひろ