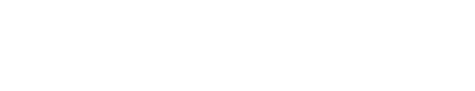家賃滞納者への対応と強制退去の手続き
賃貸賃貸物件目次
はじめに
家賃滞納者への対応は、賃貸物件のオーナーや管理会社にとって重要な課題です。家賃を支払わない賃借人に対して、適切な対応を行うことが求められます。本記事では、家賃滞納者への対応の流れや強制退去の手続きについて解説します。
賃貸物件の運営において、家賃滞納は避けられない問題の一つです。家賃滞納が発生すると、オーナーや管理会社は収入が減少し、物件の維持管理に支障をきたすことがあります。そのため、家賃滞納者に対して迅速かつ適切な対応を行うことが重要です。
家賃滞納者への対応には、まずは賃借人とのコミュニケーションが重要です。賃借人が家賃を滞納している理由を確認し、支払いの意思があるかどうかを確認します。場合によっては、賃借人が一時的に経済的な困難に直面していることもあります。そのような場合には、賃借人と協力して支払い計画を立てることが求められます。
しかし、賃借人が支払いの意思を示さない場合や、催促に応じない場合には、法的手続きを行う必要があります。法的手続きには、内容証明郵便の送付や訴訟の提起が含まれます。最終的には、裁判所の判決に基づいて強制退去を行うことになります。
家賃滞納者への対応の流れ
家賃滞納者への対応は、以下の段階を経て行います。
催促と通知
家賃滞納が発生した場合、まずは賃借人に対して催促を行います。催促は、電話やメール、郵便などで行うことができます。催促の際には、家賃滞納の理由を確認し、支払いの意思があるかどうかを確認します。
催促の際には、賃借人とのコミュニケーションが重要です。賃借人が家賃を滞納している理由を確認し、支払いの意思があるかどうかを確認します。場合によっては、賃借人が一時的に経済的な困難に直面していることもあります。そのような場合には、賃借人と協力して支払い計画を立てることが求められます。
催促の際には、賃借人に対して丁寧かつ冷静に対応することが重要です。賃借人が家賃を滞納している理由を確認し、支払いの意思があるかどうかを確認します。場合によっては、賃借人が一時的に経済的な困難に直面していることもあります。そのような場合には、賃借人と協力して支払い計画を立てることが求められます。
内容証明郵便の送付
催促に応じない場合、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便には、家賃滞納の事実と支払いを求める旨を記載します。また、支払い期限を指定し、その期限までに支払いがない場合は法的手続きを行う旨を通知します。
内容証明郵便を送付する際には、以下の点に注意することが重要です。まず、内容証明郵便には、家賃滞納の事実と支払いを求める旨を明確に記載します。また、支払い期限を指定し、その期限までに支払いがない場合は法的手続きを行う旨を通知します。さらに、内容証明郵便の写しを保管し、後の手続きに備えます。これにより、賃借人が通知を受け取ったことを証明できます。
内容証明郵便を送付する際には、賃借人に対して丁寧かつ冷静に対応することが重要です。賃借人が家賃を滞納している理由を確認し、支払いの意思があるかどうかを確認します。場合によっては、賃借人が一時的に経済的な困難に直面していることもあります。そのような場合には、賃借人と協力して支払い計画を立てることが求められます。
訴訟の提起
内容証明郵便を送付しても支払いがない場合、訴訟を提起します。訴訟の提起には、弁護士のサポートが必要な場合が多いです。訴訟を通じて、家賃滞納者に対して強制退去を求めることができます。
もっとも、裁判所は賃貸借契約のような継続的契約について、貸主・借主相互の信頼関係のうえに成立っているとして、この信頼関係を破壊するに至ったと認められるような事情がなければ、なかなか賃貸借契約の解除は許容されません。賃貸借契約書には、「貸主は、借主が賃料その他の債務の支払いを1か月以上怠ったとき、何らの催告なしに契約を解除することができる。」というような契約解除条項が入っているのが一般的ですが、契約書に1か月と書いてあったとしても、通常、1か月賃料を滞納しただけで契約を解除して出ていってもらうことは難しいです。
実務感覚では、最低でも滞納3ヶ月、長ければ6ヶ月の滞納が必要と言う場合もあります。したがって、明け渡しを求めるのは滞納が3ヶ月を超えた頃になります。ので、その前後で弁護士にご相談ください。
訴訟を提起する際には、以下の点に注意することが重要です。まず、訴訟を提起する前に、必要な書類を準備します。書類には、家賃滞納の証拠や賃貸契約書、内容証明郵便のコピーなどが含まれます。訴訟を提起する際には、弁護士のサポートを受けることが多いですので、訴状の作成や裁判所での手続きは弁護士がすることが多いです。
また、賃料不払いによる建物明け渡しの裁判を行う上で重要なことは、後の強制執行を見据えた判決の取り方です。明け渡しの範囲や滞納家賃の範囲等、訴状の中身に不備があると判決の内容が不十分になることもありますので、そのようなことが内容に請求趣旨の表現には細心の注意が必要です。家賃滞納の事実の証明自体は争われないことが多いので、勝訴判決を取ること自体は難しくないことが多いです。
後の、執行の関係もありますので、裁判は弁護士にご依頼になることをお勧めします。
訴訟の提起と進行
訴訟を提起した後、裁判所での手続きが進行します。裁判所に、家賃滞納者に対して強制退去を命じる判決を下してもらうことが目的です。
訴訟を提起した後、裁判所での手続きが進行する際には、以下の点に注意することが重要です。まず、裁判所での手続きには時間がかかることがあります。そのため、訴訟を提起する前に、賃借人との交渉を試みることが重要です。次に、裁判所での手続きには、弁護士に依頼することがほとんどだと思われますので、弁護士が、裁判所での手続きをしてくれます。
強制退去の実行
裁判を起こして建物明渡の判決をもらうことになりますが、判決をもらっても出ていってくれない人は残念ながら相当数います。任意で出てもらえない場合は、強制執行の手続きをとり、強制的に退去をしてもらい明け渡しを実現することになります。
強制執行の手続きは、明け渡しの訴訟とは別の手続きになりますので、別途申立が必要です。
強制執行の申立てを行うにあたっては、「債務名義」、「執行文」、「送達証明書」の三つが必要になります。
「債務名義」とは、建物の明け渡しを認める公の文書のことで、主に「確定判決」、「仮執行宣言付きの判決」のことを指すことが多いです。
「執行文」とは、債務名義に基づく執行が認められること示すため、債務名義の正本の末尾に付記される文言のことです。つまり、判決を言渡した裁判所の書記官に申立てをして、判決の末尾に「執行文」というものを付けてもらう手続が必要ということです。
「送達証明書」とは、債務名義が相手方に送達されたことを証明する裁判所の書面のことです。法律上、この「送達証明証」が必要になります。
この三つが揃ったら、物件所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対して強制執行の申立を行います。強制退去は、裁判所の執行官が行います。
申立を行うと執行官と打ち合せをします。打ち合せで明け渡しの催告の日程や、執行補助者をどうするのかなどという必要事項を決めます。
明け渡しの催告の日には、執行官が現地に赴き、まず、「いついつまでに明渡しなさい。」という警告と貼紙をします。その日は、とりあえず、それで終了です。
明け渡しの催告を受けると、かなりの借主がいよいよ退去が避けられないと思いますので、任意で出て行ってくれる人も多いです。
それでも、出て行ってくれない場合は、いよいよ明渡を強制執行します。
明渡の強制執行は、催告のときに執行官が定めた明渡期日(この日を断行日といいます。)に行います。まず、現地に行き、まだ明渡されていないことを確認します。建物内の物を運び出し、業者に保管させる措置がとられます。必要があれば鍵も強制的に解錠します。運び出された荷物は執行官が指定する保管場所に1か月程度保管した後、売却処分されるのが通常です。断行の際の荷物の運び出しや解錠などは執行補助者が行いますが、その費用や手配は基本債権者の負担です。荷物の保管場所の手配や費用も同様に債権者の負担です。
債権者が負担した強制執行費用や、未払賃料は、借主に請求することができますが、月々の賃料を支払えなくなっているような状態の人ですから、回収するのは困難です。そこで大事なのが、保証人です。近ごろは、保証会社が保証するケースも増えています。貸主は保証人に対する請求も怠らずする必要があります。
強制退去のメリットとデメリット
強制退去には、以下のメリットとデメリットがあります。
メリット
家賃滞納者を迅速に退去させることができる
賃貸物件を再度賃貸することができる
家賃滞納の問題を解決することができる
強制退去のメリットには、家賃滞納者を迅速に退去させることができる点があります。家賃滞納者が退去することで、賃貸物件を再度賃貸することができ、収入を確保することができます。また、家賃滞納の問題を解決することで、賃貸物件の運営を円滑に進めることができます。
デメリット
訴訟費用や弁護士費用がかかる
訴訟手続きに時間がかかる
家賃滞納者との関係が悪化する可能性がある
賃料の不払いが発生してから、明渡の強制執行が完了するまでには、1年くらいかかってしまうことも多いです。執行費用を借主や保証人に請求することはできますが、明渡の裁判を依頼するときの弁護士費用や借主が置いていった動産の保管費用は貸主が負担することになります。多くの動産を放置したまま借主が逐電してしまった場合など、弁護士費用と保管費用で合計100万円くらいかかってしまうこともありますが、自力救済が認められていない日本の法制度下では、借主の持ち物を勝手に処分してしまうことはできないため、健全な賃貸業を継続するためには、致し方ないことだと思います。
以上のように、家賃滞納から強制執行完了までの手続きは、煩雑で手間や時間がかかります。弁護士に依頼せず、一般の方が行うのは難しいと思われる場合が多いと思います。
強制執行の具体的な事例
事例1: 家賃滞納による強制退去
ある賃借人が家賃を3ヶ月以上滞納し、オーナーからの催促にも応じなかったため、オーナーは内容証明郵便を送付しました。しかし、それでも賃借人が家賃を支払わなかったため、オーナーは裁判所に訴訟を提起しました。裁判所はオーナーの主張を認め、強制退去の命令を出しました 。その後、執行官が現地に赴き、賃借人に対して明け渡しの催告を行いましたが、賃借人は任意で退去しませんでした。最終的に、執行官が強制的に建物内の物を運び出し、物件を明け渡しました 。
事例2: 長期滞納による強制執行
別の事例では、賃借人が6ヶ月以上家賃を滞納し、オーナーからの連絡にも応じませんでした。オーナーは弁護士を通じて裁判所に訴訟を提起し、強制退去の判決を得ました。その後、執行官と打ち合わせを行い、明け渡しの催告を実施しましたが、賃借人は依然として退去しませんでした。執行官は断行日を設定し、強制的に建物内の物を運び出し、物件を明け渡しました 。
事例3: 保証人を通じた解決
ある賃借人が家賃を4ヶ月滞納し、オーナーからの催促にも応じませんでした。オーナーは内容証明郵便を送付し、裁判所に訴訟を提起しました。裁判所はオーナーの主張を認め、強制退去の命令を出しました 。しかし、賃借人が退去しなかったため、オーナーは保証人に対して請求を行いました。保証人が賃借人に対して支払いを促し、最終的に賃借人は任意で退去しました 。
事例4: 動産の保管と売却
ある賃借人が家賃を5ヶ月滞納し、オーナーからの連絡にも応じませんでした。オーナーは裁判所に訴訟を提起し、強制退去の判決を得ました。執行官が明け渡しの催告を行いましたが、賃借人は退去しませんでした。断行日に執行官が現地に赴き、建物内の物を運び出し、指定された保管場所に保管しました 。その後、保管期間が過ぎたため、運び出された荷物は売却処分されました。
強制退去の事例からは、家賃滞納者が退去を拒否した場合、裁判所の判決に基づいて強制退去を行いますが、それには多くの費用と時間がかかることがわかります。
まとめ
家賃滞納者への対応と強制退去の手続きは、賃貸物件のオーナーや管理会社にとって重要な課題です。適切な対応を行うことで、家賃滞納の問題を解決し、賃貸物件の運営を円滑に進めることができます。
家賃滞納者への対応には、まずは賃借人とのコミュニケーションが重要です。賃借人が家賃を滞納している理由を確認し、支払いの意思があるかどうかを確認します。場合によっては、賃借人が一時的に経済的な困難に直面していることもあります。そのような場合には、賃借人と協力して支払い計画を立てることが求められます。
しかし、賃借人が支払いの意思を示さない場合や、催促に応じない場合には、法的手続きを行う必要があります。法的手続きには、内容証明郵便の送付や訴訟の提起が含まれます。最終的には、裁判所の判決に基づいて強制退去を行うことになります。
強制退去の手続きには、以下のメリットとデメリットがあります。メリットには、家賃滞納者を迅速に退去させることができる点があります。家賃滞納者が退去することで、賃貸物件を再度賃貸することができ、収入を確保することができます。また、家賃滞納の問題を解決することで、賃貸物件の運営を円滑に進めることができます。
一方、デメリットには、訴訟費用や弁護士費用がかかる点があります。訴訟を提起する際には、弁護士のサポートが必要であり、その費用がかかります。また、訴訟手続きには時間がかかることがあります。さらに、家賃滞納者との関係が悪化する可能性があります。
さらに家賃滞納者が退去を拒否した場合、裁判所の判決に基づいて強制退去を行うケースもあり、その場合は更に時間と費用がかかります。
家賃滞納者への対応と強制退去の手続きは、賃貸物件のオーナーや管理会社にとって重要な課題です。適切な対応を行うことで、家賃滞納の問題を解決し、賃貸物件の運営を円滑に進めることができます。
「追記」交渉の重要性 ~話合いの余地があります~
上記したような建物明渡の裁判をし、強制執行をするには多額の費用や長い時間がかかります。
そのことを考えれば、任意に借主が出て行ってくれた方が圧倒的に有利です。その為、スムースな明け渡しの為に貸主が譲歩し交渉により出て行ってもらうことを検討する余地も充分あります。
いずれにしても、弁護士に相談してみて下さい。法律的な解決方法が見出せるはずです。
川崎合同法律事務所 弁護士 星野文紀