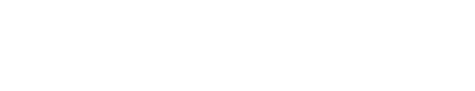借地非訟とはなんですか
借地賃貸借地非訟とは
借地非訟は、土地を借りている借地権者と土地を貸している借地権設定者との間での借地関係において紛争が発生した際に、裁判所の手続の下で、借地権者と借地権設定者との間の話し合いの成立、借地権設定者の承諾に代わる許可等の裁判を行うことによって、柔軟かつ迅速に紛争を解決するための手続であり、非公開の手続となっています。
借地非訟の手続では、借地契約のうち旧借地法及び借地借家法に定められた借地権を扱い、建物の所有を目的とする土地賃貸借契約又は地上権設定契約であることが必要となります。そして、借地契約を締結した時期によって、旧借地法が適用されるのか、借地借家法が適用されるのかが変わることになります。
借地非訟の種類
借地非訟事件として扱うことができるものは、主に次の6種類に分けられます。
⑴ 借地条件変更申立(借地借家法第17条第1項)
この類型は、借地契約に、建物の種類(居宅・共同住宅等)、構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)、規模(床面積等)又は用途(事業用等)を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときに、借地権者または借地権設定者から申し立てられるもので、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる、というものです。
⑵ 増改築許可申立(借地借家法第17条第2項)
この類型は、増改築を制限する旨の借地条件が定められている場合に、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときに、借地権者から申立てられるもので、裁判所はその申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる、というものです。
増築とは、既存の建物に工作を加えて床面積を増加させる、既存の建物に付加して付属建物や別個の建物を建築するものをいいます。改築とは、既存の建物を取り壊して新たに建物を建築するものをいいます。
この類型については、借地条件変更の申立て、土地賃借権譲渡又は転貸の許可申立てとともに申し立てられることがあります。
⑶ 更新後の建物再築許可申立事件(借地借家法第18条第1項)
この類型は、借地契約の更新後に、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときに、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、借地権者から申し立てられるものであり、裁判所はその申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可の裁判をすることができる、というものです。
この類型は、借地借家法によって新設されたもので、借地借家法の施行後に設定された借地権についてのみ適用され、借地借家法施行前に設定された借地権については適用されません(借地借家法附則第11条)。
⑷ 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法第19条第1項)
この類型は、借地権者が、土地賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、民法上、借地権設定者の承諾を得る必要がありますが、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に振りとなるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときに、借地権者から申立てられるものであり、裁判所は、その申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができ、この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、付随処分として、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができます。
⑸ 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法第20条第1項)
この類型は、第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときに、その第三者から申立てられるものであり、裁判所は、その申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができ、この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、付随処分として、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができます。
ただし、上記申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができます(借地借家法第20条第3項)。
⑹ 借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件(借地借家法第19条第3項、第20条第2項)
この類型は、上記「⑷ 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法第19条第1項)」の申立てをした場合、又は上記「⑸ 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法第20条第1項)」の申立てをした場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときに、裁判所は、その申立てにより相当の対価及び転貸の条件を定めて、第三者に対する賃借権の譲渡に優先して借地権設定者に対する建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を命ずることができる、というものです。この裁判において、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができます(借地借家法第19条第3項、借地借家法第20条第2項)。
この類型は、借地権設定者に介入権を認めたものです。借地権設定者から、上記申立てがあると、裁判所は、相当の対価を定めて借地権設定者に対して建物と賃借権を譲渡することを命ずる裁判をして、上記「⑷ 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法第19条第1項)」の申立て又は上記「⑸ 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法第20条第1項)」の申立ては、何らの裁判もされないまま、終了します。
借地権設定者の介入権行使の申立てについては、上記「⑷ 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法第19条第1項)」の申立て又は上記「⑸ 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法第20条第1項)」の申立てが取り下げられたとき、又は不適法却下されたときは、その効力を失います(借地借家法第19条第4項、借地借家法第20条第2項)。
また、借地権設定者の介入権行使の申立てに対する裁判があった後は、上記「⑷ 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法第19条第1項)」の申立て又は上記「⑸ 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法第20条第1項)」の申立ては、いずれも当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができません(借地借家法第19条第5項、借地借家法第20条第2項)。
借地非訟事件の手続
⑴ 借地非訟事件は、当事者の申立てによって手続は開始されます。申立ては書面によることになります。
当事者からの申立てにより、借地非訟事件が裁判所に係属すると、申立てが明らかに不適法であって補正することができないときを除き、裁判所は、申立書を相手方に送達します。
⑵ 裁判所は、第1回審問期日を定めることになります。第1回審問期日は、申立書を相手方に送達した後、特別の事情がない限り、速やかに開くべきものとされています。
審問期日においては、当事者の陳述を聴き、裁判所が争点及び証拠の整理をして審理の計画を立てます。当事者からは、陳述を記載した書面、証拠等が提出されます。
借地非訟事件は、職権探知主義となっており、裁判所は職権で事実の調査をし、また、証拠調べをすることができます。そして、借地非訟事件の手続は非公開となっており、審問期日は、一般には公開されません。
⑶ その後、必要に応じて、第2回以降の審問期日が開かれ、同様に当事者からは、陳述を記載した書面、証拠等が提出される、裁判所が事実の調査をする等して、審理が進行します。
借地非訟事件が進行する中で、和解が成立する場合には、和解成立により事件終了となることもあります。
⑷ 裁判所が、終局決定をする場合には、特に必要がないと認める場合を除き、鑑定委員会の意見を聴かなければならないこととなっています。鑑定委員会の意見を聴くべき事項は、申立てに対する裁判や付随処分をする上での事項(許可の可否に関する事情、承諾料、借地権設定者が建物及び賃借権の譲渡を受ける場合の対価等)ということになります。
鑑定委員会は、意見形成に当たって、裁判所が事実調査や証拠調べ等によって調査確定した事実関係のほか、独自に必要な限度で事実調査を行うことができます。また、鑑定委員会は、現地調査を行います。
そして、鑑定委員会は、原則として主文及び理由を記載した書面によることになり、その意見書は裁判所に提出されて記録に編綴され、当事者は閲覧謄写することができます。
⑸ そして、裁判所は、借地非訟事件が裁判をするのに熟したときは、審理を終結して終局決定をします。借地非訟事件においては、裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言します。
裁判所の終局決定は、裁判書を作成していなければなりません。終局決定は、申立てを認容するものと申立てを排斥するものがあります。なお、申立てを認容する裁判には、申立てそのものについてされる裁判と、これに伴う付随処分に関する裁判があります。
借地非訟事件の終局決定は、その正本を当事者に送達することが必要となります。
借地非訟事件の終局決定に対し、即時抗告がなされた場合には、抗告審において審理がなされることになります。
監修 弁護士 小林展大
この記事と関連するコラム