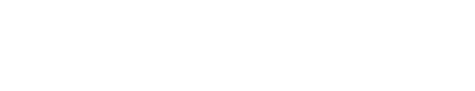その財産、動きますか? ~「不動産」と「動産」の知られざる名前の秘密~
その他・読み物私たちの生活は、さまざまな「財産」であふれています。夢のマイホームや親から受け継いだ土地、毎日乗る自動車、お気に入りのスマートフォンや洋服まで。これらの財産が、法律の世界では大きく「不動産」と「動産」の二種類に分けられていることをご存知でしょうか。
「不動産屋さん」という言葉は日常的に使いますし、なんとなく「不動産=土地や建物」「動産=それ以外のモノ」というイメージをお持ちかもしれません。その理解は、まさに正解です。
しかし、なぜわざわざ「動かない財産」「動く財産」と名付けられているのでしょうか。そこには、古代ローマから続く、世界の法制度の根幹に関わる深い理由と、言葉の面白い歴史が隠されていました。今回は、そんな身近な言葉のルーツを探る旅に出かけてみましょう。
目次
◆ 日本の法律に刻まれたシンプルな定義
まず、私たちの国のルールブックである法律を見てみましょう。民法という法律に、そのものズバリの答えが書かれています。
民法第86条
- 土地及びその定着物は、不動産とする。
- 不動産以外の物は、すべて動産とする。
非常にシンプルですね。
「土地と、そこにガッチリと固定されているもの(建物、橋、石垣など)」が不動産。そして、それ以外は全部まとめて動産。これが日本の法律における定義です。
この条文からも、「物理的に動かせるかどうか」が名前の由来であり、分類の基準であることが一目瞭然です。「不動産」「動産」という漢字も、その性質をストレートに表現していて、非常に分かりやすいネーミングと言えるでしょう。これらの言葉は、明治時代に近代的な法律を整備する過程で、西洋の法律概念を翻訳して作られた法律用語です。では、その翻訳元である西洋では、これらの財産を何と呼んでいたのでしょうか。
◆ 言葉の源流へ:ドイツ語から古代ローマへ
日本の民法は、主にドイツやフランスの法律を参考に作られました。そこで、ドイツ語を覗いてみることにします。
- 不動産:Immobilien (インモビーリエン)
- 動産:Mobilien (モビーリエン)
何となく響きが似ていますね。それもそのはず、これらの単語は共通のパーツからできています。
「動産」にあたる Mobilien は、「動くことができる」という意味のラテン語 mobilis に由来します。英語の mobile(モバイル)と同じ語源です。まさに「動くもの」ですね。
一方、「不動産」の Immobilien は、この mobilis に、否定を表す接頭辞 im- が付いた形です。つまり im-mobilis で「動くことができないもの」という意味になります。
なんと、ドイツ語でも日本語の「不動」「動」と全く同じ発想でネーミングされていたのです。この考え方は、さらに古代ローマ時代のラテン語にまで遡ることができます。古代ローマ法では、物を res immobiles(動かない物)と res mobiles(動く物)に区別していました。res は「物」を意味します。
つまり、「不動産」と「動産」という区別は、ヨーロッパの法の源流であるローマ法の時代から、その物理的な性質(動くか、動かないか)に着目した、普遍的なアイデアだったのです。
◆ ちょっと寄り道:英語のユニークな世界観
ところが、同じヨーロッパでも、英語圏では少し違うユニークな言葉が使われています。
- 不動産:Real estate / Real property
- 動産:Personal property / Chattel
「動く・動かない」という直接的な表現ではありませんね。ここには、イギリスの歴史が色濃く反映されています。
Real estate の Real の語源は、ラテン語の res(物)に由来するとも、regalis(王に属するもの)に由来するとも言われています。中世の封建社会において、土地は究極的には国王の所有物であり、そこから派生する権利こそが「本来的(Real)な財産」と見なされていました。
それに対して、土地以外の財産は Personal property、つまり「個人的な(Personal)財産」と呼ばれました。
さらに面白いのが、動産を指すもう一つの単語 Chattel です。この言葉、実は「牛」を意味する Cattle と同じ語源なのです。大昔のヨーロッパでは、家畜、特に牛が富の象徴であり、主要な動く財産でした。その名残が、現代の法律用語にひっそりと息づいているとは、なんとも興味深い話です。
◆ なぜ「動くか」が、それほど重要なのか?
さて、古代ローマから現代の日本に至るまで、なぜこれほどまでに「動くか、動かないか」という性質にこだわって財産を区別するのでしょうか。それは、この区別が財産の権利を誰かに主張するためのルールと密接に結びついているからです。
あなたが家を買ったときのことを想像してみてください。その家が本当にあなたのものだと証明するにはどうすればいいでしょうか。「この家は私のものです!」と叫んでみても、誰も信じてくれません。そこで登場するのが「登記」です。不動産は、法務局という公的な機関に「この土地・建物は、誰が所有者です」と登録(登記)することで、社会全体に対して「これは私のものだ」と主張(対抗)できるようになります。高価で重要な財産だからこそ、このような厳格な公示制度が採用されているのです。物理的に動かないからこそ、場所を特定して記録する「登記」というシステムと相性が良いのです。
では、コンビニで買ったおにぎりはどうでしょう。いちいち法務局で所有権の登記などしていたら、日が暮れてしまいます。動産の場合、権利を主張するための方法はもっとシンプルです。それは「引渡し」、つまり実際に物を受け取って持っている(占有している)ことです。あなたがそのおにぎりを手に持っていれば、周りの人は「ああ、それはあなたのものなのだな」と認識します。
- 不動産:動かせない → 「登記」で公示する
- 動産:動かせる → 「引渡し」で公示する
このように、物の物理的な性質の違いが、私たちの財産権を守るための法的な仕組みの違いに直結しているのです。「不動産」「動産」という名前は、単なる呼び名ではなく、その財産を扱うための根本的なルールを示す、重要なキーワードだったのですね。
◆ おわりに
「不動産」と「動産」。その名前は、古今東西を問わず、「動くか、動かないか」という極めてシンプルで物理的な特徴に由来していました。そして、そのシンプルな区別が、登記や引渡しといった、現代社会における財産取引の安全を支える、洗練された法制度の土台となっています。
何気なく使っている言葉の語源をたどると、そこには壮大な歴史や、社会を成り立たせるための先人たちの知恵が隠されています。次に「不動産」という言葉を見聞きしたとき、その奥にある古代ローマの街並みや、中世ヨーロッパの牛たちの姿に、思いを馳せてみるのも一興かもしれません。
監修:弁護士 畑福生
この記事と関連するコラム
関連記事はありません